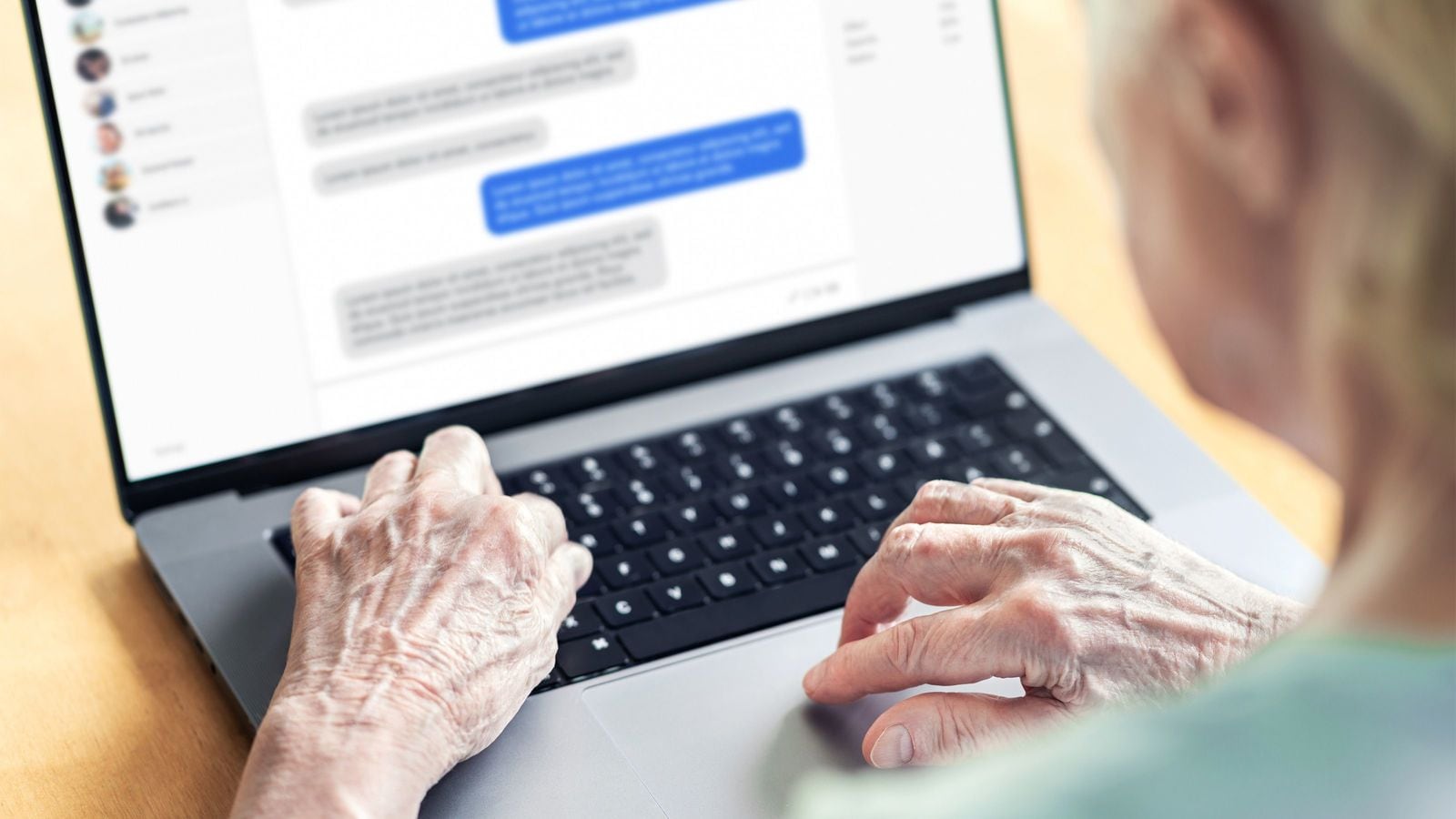選挙期間中に選挙報道が減る新聞
――参議院選挙を前に、日本新聞協会は、メディアが公平性を過度に意識せずに、選挙期間中も積極的に報道するという声明を発表しました。背景には、不正確な情報によって選挙結果が左右される状況があるようです。
そもそも論として、ぼくには、オールドメディアと呼ばれる新聞や、テレビの報道は本当に公平だったのか、という疑問があります。
新聞やテレビが主に取り上げるのは、主要候補者ばかりです。確かに、主要政党の候補者をあつかう場合は、同じ行数の記事にしたり、同じ時間を使って取り上げたりして公平を意識したのでしょう。いえ、意識せざるを得なかった。そうしないと政党からクレームが入りますから。一方で主要候補者以外は、せいぜい名前や肩書、年齢くらいで、主張や政策を丁寧には伝えてこなかった。
とはいえ、それが間違いだと言っているわけではありません。各メディアによって、それぞれ報道のあり方や方針があります。そうした大手メディア以外の情報があったほうがいいだろうと考え、ぼくは「候補者全員に接触」を信条に選挙取材を続けてきました。
日本新聞協会の声明で注目したいのが、後半の選挙期間中も積極的に報道するという箇所です。裏を返せば、選挙期間中にもかかわらず、逆に選挙についての報道が減っているということです。
オールドメディアがSNSに敗北した原因
――それは、なぜなのでしょうか。
わかりやすい例が、昨年11月の兵庫県知事選です。選挙前、新聞やテレビは、斎藤元彦知事の批判を散々報じました。しかし県知事選が告示されるとパタッと批判しなくなった。それは、大手メディアが選挙に影響を与えるような報道を控えたからです。
加えて、新聞やテレビは、確かな情報だとしても、一度報じたニュースは基本的に繰り返しません。そこが、兵庫知事選で、オールドメディアが、SNSやインターネットに敗北した原因です。